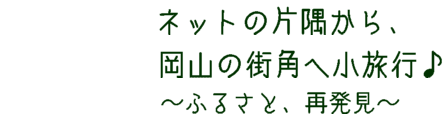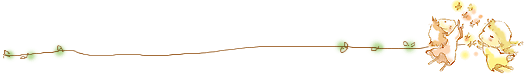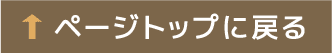TOP>備中県民局エリアの地名の由来>浅口市・寄島地域

地名の由来:寄島地域
地名の由来
浅口市の寄島地域の地名の起源は、周辺がまだ島だった頃まで遡ります。
当地には神功皇后が朝鮮遠征の帰りに、風光明媚な島があると 知って立ち寄ったという言い伝えがあります、
神功皇后が立ち寄った島という意味で『寄島』と呼ばれるようになったのです。
尚、神功皇后が寄港した場所は、現在の寄島地域の陸続きになっている部分ではなく、後述する三郎島です。
元々は三郎島のことを寄島としていたのが、周辺の地区が村を形成したときに、新しい村名として寄島を採用したのです。
三郎島
前述のように寄島が村の名前に採用された後、神功皇后が寄港した元々の寄島は『三郎島』と呼ばれるようになりました。
これは近くにあった小島の名称で、現在『三ツ山』 と呼ばれている島がこれに当たります。
その形からか、神功皇后が落としたおむすびが島になったという伝説が残されています。
周辺には寄島と同様に神功皇后が訪れた事に由来するといわれる地名も幾つか残っています。(例えば安倉は休息を取った事が由来とされています)
※神功皇后とは仲哀天皇の皇后です。
応神天皇を産んだとされていますが、その実在性には疑問が残されています。
全国各地に逸話が残されており、岡山県内にも朝鮮遠征へ向かう途中の行程のエピソードがいくつか残されています。
より姉妹外にも牛窓、玉島、胸上などの地名の起源にも 関わっています。