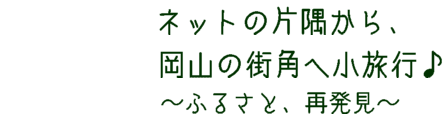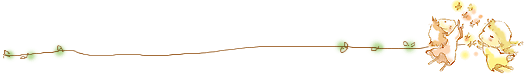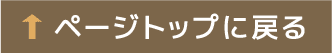TOP>岡山のパワースポット>吉備津神社

備中国一宮・吉備津神社
詳細
主祭神:大吉備津彦命
別名、愛称:吉備津宮、朝日の宮
旧社格:国幣小社
備前国の一宮
所在地:岡山市北区一宮1043
駐車場:有り、無料
参拝は24時間可
備中国一宮
岡山市北区に位置する吉備津神社は、備中国の一宮として深い歴史と信仰のある神社です。「一宮」とはかつての令制国(日本の行政区分)の中で最も社格が高い神社を指します。
これらの神社は、地域に根ざした守護神として古くから信仰されており、その歴史的・宗教的な重要性が高く評価されています。
一宮には各令制国において地域住民から特に尊敬され、信仰を集めた神社が選ばれる傾向があります。
吉備津神社は備中国内でその位置を確立し、地域の人々にとって吉備津神社は心の拠り所となり、今日に至るまで多くの参拝者を迎えています。
3つの吉備津神社
吉備津神社の近くに位置する吉備津彦神社は、その名前が似ているため、しばしば混同されがちです。実は吉備津彦神社は吉備津神社から分霊されて誕生した経緯があります。
元々、吉備津神社は吉備国(現在の岡山県とその周辺)の総鎮守として信仰されていました。吉備国が後に備前国、備中国、備後国の三つに分かれることになり、誕生した三つの国に吉備津神社が分霊されて、それぞれの土地で崇められるようになりました。
具体的には、吉備津彦神社は備前国に、広島県福山市にある吉備津神社は備後国の守護神として分霊されました。元々の吉備津神社は、備中国の一宮となりました。
大吉備津彦命
主祭神は大吉備津彦命です。
大吉備津彦命は、桃太郎伝説の起源となったとされる、周辺を支配していた温羅との戦いで知られる神様です。
一説には吉備津彦命が大和政権から派遣されてきて、吉備王国の支配者を倒し、吉備の国を平定した経緯が温羅伝説になっているとも言 われています。
温羅との戦いの後に吉備の国を治めて、後に神社の裏に広がる吉備の中山に築かれた中山茶臼山古墳に葬られたとされています。
国宝・重要文化財
・本殿拝殿
本殿と拝殿は接続しており、1つの建物として国宝に認定されています。

創建時から2度焼失しており、現在の建物は1425年に再建されたものです。
規模は全国屈指の大きさで、入母屋造の屋根が二つ連なる独特の作りから吉備津造りとも呼ばれます。
・御釜殿
鳴釜(後述)の神事に用いられる場所で、国の重要文化財です。
こちらも一度再建された建物です。
・北随神門、南随神門
どちらも国の重要文化財にしていされています。
北随神門は、1543年に再建された入母屋造りの神門で、北参道(駐車場側)から入る際に通る場所です。
南随神門は1357年と、神社にある建物の中でもひときわ古い建物です。
後述する回廊の途中にあります。
・廻廊
本殿からへ御釜殿向かう途中にある、全長360mほどもある回廊です。
一直線に続きますが、なだらかに傾斜しているのは、自然の地形そのままに作られているからです。
1579年に再建された建物で、県の重要文化財に指定されています。
温羅伝説と神事
吉備津神社には温羅伝説にまつわる神事が伝えられています。
・鳴釜神事
先に紹介した御釜殿で行われる神事です。

湯を沸かした釜に、お米を投じると釜から音が出ます。
音の大きさ、長さから吉凶を占うというものです。
言い伝えでは、吉備津彦命に負けた温羅の首が御釜殿の地下に埋められて尚、唸り続けていましたが、温羅の妻の出身地である阿曽の女 性がお米を炊く儀式を行った際に、吉凶を伝えるようになったと言われています。
・矢立の神事
温羅と吉備津彦の戦いで描かれている、矢の打合いに由来する神事です。
矢を放つ事で、悪いものを払うというもので、無病息災を願う行事です。
鳴釜神事は毎週金曜日以外は実施されています。(有料、2015年12月現在)
矢立の神事は1月3日の朝早くから行われていますので、興味がある方は、それぞれ問い合わせて見て下さい。