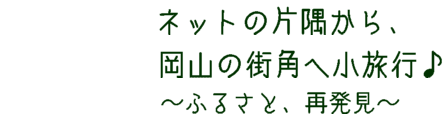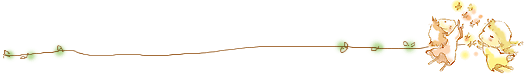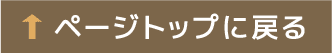TOP>美作県民局エリアの地名の由来>津山市

地名の由来:津山市
津山市 概略
市名:津山市(Tsuyama)
市の花:サクラ、サツキ
市の木:クスノキ
関連リンク:津山市公式HP
浅見光彦シリーズ・歌わない笛(津山市が舞台の作品)
地名の由来
津山の地名は初代津山藩主である森 忠政が美作国の領主として入封した時に、津山盆地のほぼ中心に位置する鶴山に築城をした事に由来します。
ここまでは岡山城同様(岡山の地名も城の建てられた地名による)の流れです。
しかし鶴山の『鶴』は、森家の家紋だったので、そのまま鶴山とはせず改称することになりました。
そこで鶴を訓読みにして『津山』と改名しました。これは改名ではなく、津山としていたのを同地で山名氏が築城した際に鶴山としたのを戻したとも言われています。
戻した理由の一つには津の方が鶴より漢字が平易であるという判断があったともいわれています。(津山市史6現代1明治時代より)
『津』という字には船着場や港の意味があります。運河で栄えた津山の風土と関係しているのでしょう。
ただし鶴山から津山への改称の経緯ははっきり伝わってはおらず、どいういう理由で変わったのかは今後の研究次第で変わる可能性があります。
鶴山の由来
津山城は明治時代になり廃城令で取り壊されました。石垣のみが残され、『鶴山(かくざん)公園』として整備されています。春はサクラの名所として多くの観光客の目を楽しませています。
鶴山の地名は、前述の通り津山の地名を縁起のいい鶴に置き換えたとされていますが、異説として山の形が羽を広げた鶴のように見える事からきているとも言われています。
これは倉敷市美観地区中央部にある鶴形山と同じ由来です。鶴は縁起がい生き物とされているので、地名にも採られやすいのでしょう。
実際に津山と改名した後も縁起が良く風雅な響きの鶴山を使い続ける人は多く、津山が定着するようになるのは明治時代に入ってからだったそうです。
二度、県庁所在地になった津山
津山市(旧津山町)は廃藩置県の際に誕生して短期間で消滅した『津山県』と『北条県』に属していました。
津山はこの二県のどちらにおいても、県庁所在地に指定されています。
岡山県となった現在は県庁所在地ではありませんが、今でも岡山の県北、美作エリアにおける最大の都市として栄えています。