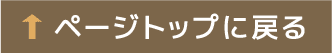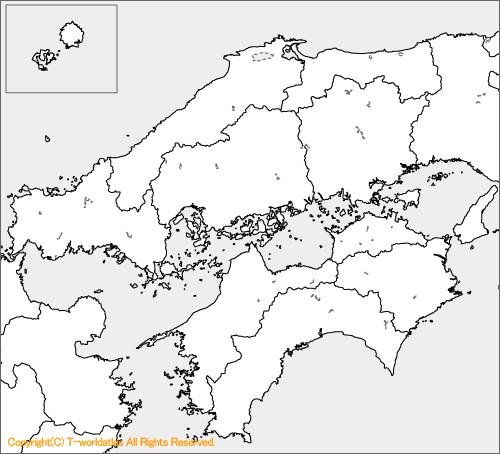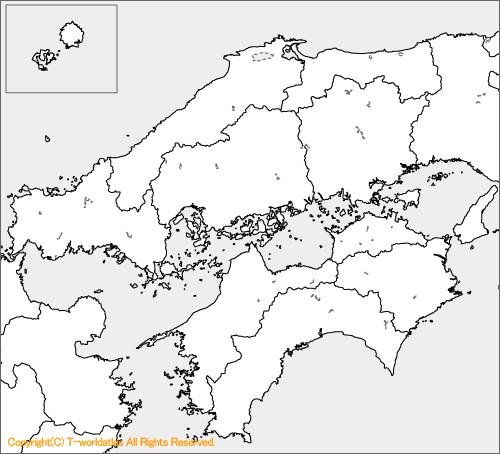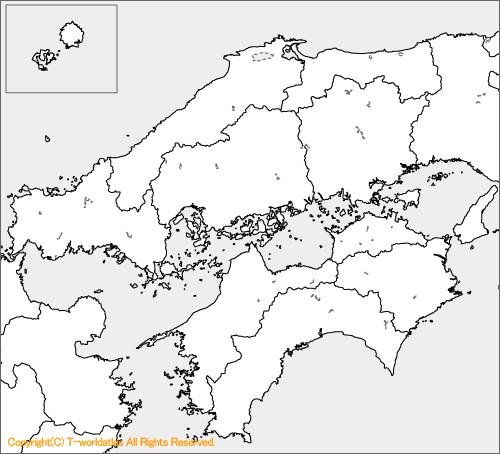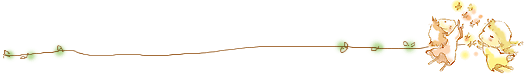吉備、備前、備中、備後の国名の由来
吉備の国の由来
岡山県の旧国名は『吉備』です。
これは黍の収穫量が多かった事に由来すると言われています。
他の国名を見ても、粟に由来する阿波国や木の国が転じて紀伊国となった例などもあり、吉備=黍も充分にあり得るでしょう。
岡山県内には大きな古墳が数多く造られている事から、出雲やヤマト王権といった日本を代表する勢力に匹敵するような巨大な力を持っている国だったと考えられています。
後に吉備の国は三つに解体され、備前、備中、備後の国に分かれました。
備前、備中、備後の由来
現在でも広域な地域を表す言葉として用いられている、旧国名である『備前』、『備中』、『備後』。
岡山県では備前、備中が県民局の名称としても用いられています。
これは吉備の国を三つに分けた際の、東部が備前、中央部が備中、西部が備後です。
吉備の国を分離した際に、『前つ国』、『中つ国』、『後つ国』と呼んだことから、やがて備前、備中、備後という国名に定着していきました。
現在では備後の地域は笠岡市用之江地区を残して、広島県(福山市周辺)へ移管されています。
三つの吉備津神社の謎
吉備津神社は元々は吉備の国の総鎮守の神社でしたが、吉備の国が三つに分けられた際にそれぞれの国へ分霊されています。
それが現在の岡山市北区吉備津にある備中国の吉備津神社(元々の吉備津神社)、岡山市北区一宮にある備前国の吉備津彦神社、そして福山市新市町宮内にある備後国の吉備津神社です。
美作国
旧吉備国内にあるもう一つの国、岡山県の東北部に位置する『美作』は、上記の三国が生まれてもう少し経ってから誕生しました。
備前、備中、備後に分かれた後、更に備前の国を分割して生まれたのが美作国です。
吉備の国を三つに分けた理由は、吉備の国を弱体化させて大和王権による支配を安定させる為です。
そこから更に備前を二つに分割したのは、まだ備前が強力すぎると判断した為なのかも知れません。
※美作国の由来はコチラ
この分割の作業は吉備国以外でも進められており、同様の理由で美作の国と同じタイミングで、丹後国や大隅国といった国も分割により誕生しています。
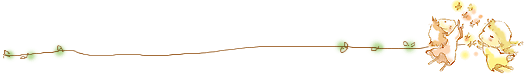
-戻る-
関連リンク
写真提供:岡山県