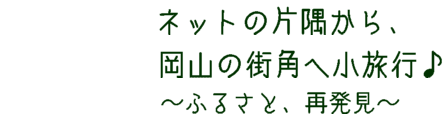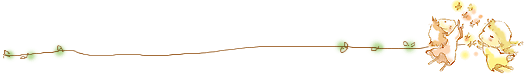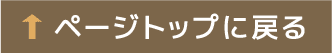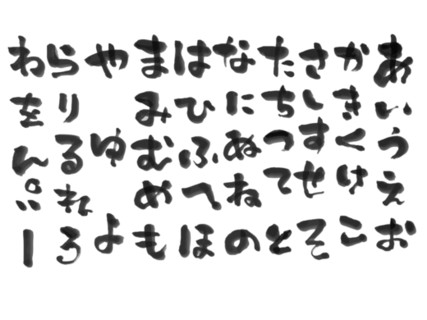
ひらがな地名の事情アレコレ
平成に増えたひらがな地名
平成の大合併の特徴としてひらがなの自治体名が増えたことが挙げられます。
ひらがなの地名が採用されるのには幾つかの理由があります。
まずはひらがなにすることで柔らかい印象を与える事が挙げられます。
本来の漢字が難しい字だったり、難読である事を理由に読み書きしやすくするなどの実用的な目的もあります。
他にも市町村合併の際に既存の市町村名を採用する場合に、ひらがなにしてしまう事で合併する全自治体が改称するという公平感を出すために用いられる場合もあります。
ただし地名の持つ本来の意味や歴史が損なわれるという事で反対する意見も少なからず存在します。
ひらがな地名の歴史
ひらがなの地名を初めて採用した自治体は、1948年に誕生した長野県の「ちの町」です。(現在は合併により茅野市)
地名は町内にある茅野駅に由来しますが、駅と実際の茅野地区は別です。
そこで本来の茅野に配慮して、ひらがなのちの町を名乗ることになりました。
1955年には本来の茅野を含む宮川村などと合併が行われ、この時に漢字の茅野町になりました。
市名では1966年に誕生した「いわき市」が初です。
14の市町村が合併して誕生しました。その中に磐城市が含まれており、吸収合併のように見られないようにとひらがなを採用しました。
興味深い事例として2010年に誕生したみよし市があります。元々は三好町で市政施行の際に徳島県に三好市が存在していました。
総務省は徳島の三好市が合意すれば同一市名を可としましたが、拒否された為にひらがなでの表記になりました。