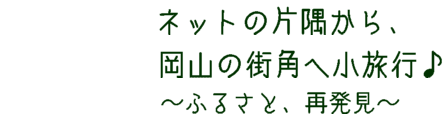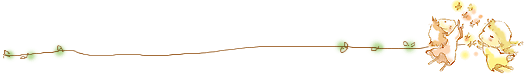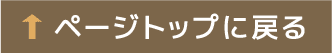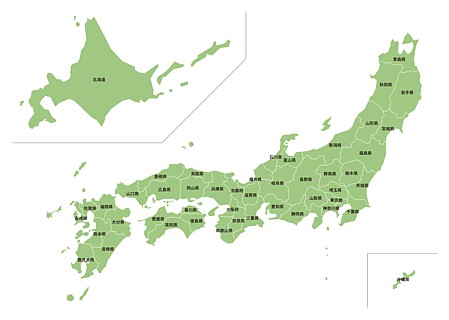
漢字二文字の地名はなぜ多い?
漢字二文字の地名が多いのは?
地名の漢字は二文字が多いと思ったことはないでしょうか?
古くからある地名には当て字のような三文字以上の地名がありました。
しかし713年に「諸国郡郷名著好字令」という命令が出ます。簡単に言うと、地名はいい意味を持つ漢字2文字にしましょうという内容です。
この事から好字二字令とも呼ばれます。
名前にもある通り対象は国、郡、郷といった広域地名でした。しかしこの影響で地名は2文字という概念が出来上がり、後に誕生した地名にも2文字の物が多くなりました。
本当は怖い〇〇地名…といった本が一時期ブームになりましたが、好字二字令の際に本来の意味から乖離した漢字に変化した地名も少なくはなかったのでしょう。
2文字にしたのは中国の地名の影響です。日本人の苗字は地名から採っているケースが多く、その為に苗字も2文字が多数になっています。
一文字も二文字へ
好字二字令によって変化したのは3文字以上の地名だけではありません。
1文字の地名も2文字になりました。
木の国は紀伊国、粟の国が阿波国など、読み方を保ったまま2文字に変化させるパターンが多かったようです。
ユニークな例としては「和泉」があります。
読み方は「いずみ」です。泉の地名を二字にするのに好字である和を添えています。ここでの和は好字二字令に対応するためだけで、発音される事はありません。
似たような事は三文字以上の地名でも行われています。二字にするのに適当な漢字が見当たらない場合は、どれか一文字を抜いて読み方はそのままに二文字の地名にしています。
地名や苗字でしか見られない読み方をする漢字は、もしかすると好字二字令に影響しているのかもしれません。