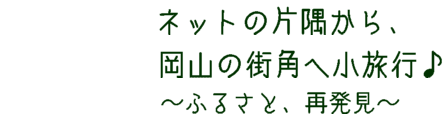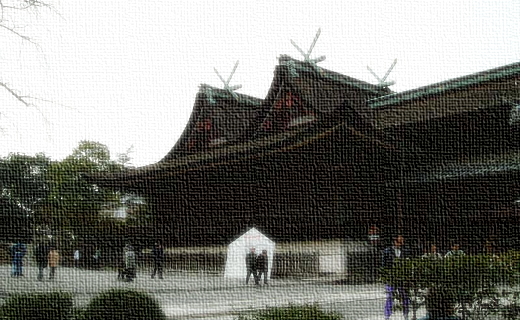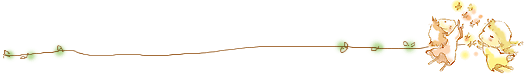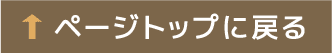霊山・吉備の中山
岡山市北区の標高175mほどの山の集まりを『吉備の中山』と呼びます。
古来より神の宿る霊山として信仰を集めました。
備前国の一宮(かつての国の範囲の中で最も格式高い神社のこと)である吉備津彦神社、備中国の一宮である吉備津神社も中山の麓に建てられています。
山の中には吉備津彦命の墓であると推測される『中山茶臼山古墳』もあります。
古今和歌集において『真金吹く 吉備の中山 帯にせる 細谷川の音のさやけさ』と詠まれ、古くから信仰されていたことが判っています。
吉備の中山の地名の由来
吉備の中山はかつての吉備の国(現在の備前、備中、備後、美作地方)の中央辺りに位置しており、その為に『吉備の中山』と呼ばれています。
鯉山(リザン)の別名もあります。
遠くから見た山容が、鯉の泳いでいる姿に似て見えるということから付けられた名称で、地元の小学校の名前等で見かけることがあります。
境目川の地名の由来
吉備の中山を流れる川に『境目川』があります。
文字通り備前の国と備中の国の国境となった川です。
神が宿る山と信じられてていた霊山なので、分割される際には備前も備中も、中山を自分の国に欲しがったと言われています。
そこで争いを避けるために、吉備の中山を二等分するように流れている境目川を国境にすることで解決したのでしょう。