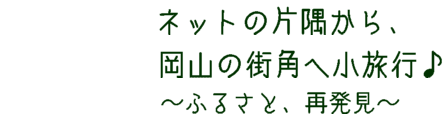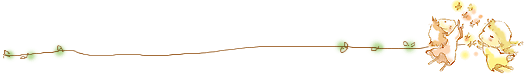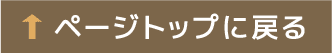TOP>備前県民局エリアの地名の由来>備前市・日生地域

地名の由来:日生
地名の由来
日生という珍しい地名の由来は二つ知られています。
一つは旧地名が『星村』というものだったいう ものです。
しかし火災が多発した為に、日(火)と生という字を離して『日生』としたというものです。
もう一つの由来は古くからあった『日那志』という漢字が転じたものです。
こちらの説の方が有力説として考えられています。
かつて往来の中心となっていた山道から、ちょうど綺麗に朝日が登ってくるのが見えることからついた地名であると考えられており、『日成』の書き方もされたそうです。
また朝日の美しい瀬で、ヒナセという名前が生じたという説もあります。
ヒナセ?ヒナシ?
かつて日那志と書いた通り、古くから『ヒナセ』と『ヒナシ』の二通りの読み方が混在していたそうで、これは書き方が現在の日生と転じてからも続きました。
現在のようにヒナセの呼び方に統一されるようになったのは、郵便局の開局の際でした。
郵便局がヒナセの読み方を採ったので、ではそれに合わせて公式にはヒナセと呼ぶようにしよう…と決まったそうです。
同じような例は各地で見られ、例えば浅口市の読みはアサクチですが、アサグチの読み方をする人も多くいます。
その為に周辺3町が合併して市の名前を公募した際にも、アサクチとアサグチの双方の読み方で応募があったそうです。
越県合併の歴史
備前市日生町は兵庫県と隣接しています。
地域によっては兵庫県との関わりが深く、過去には歴史上珍しい県境を越えての合併、越県合併が行われた事があります。
兵庫県赤穂市の福浦地区はかつて日生町の一部でした。
しかし兵庫県側との方が生活上の交流が深いとの理由から、岡山県から兵庫県に変わりました。
その歴史から、現在でも福浦地区は中国電力が兵庫県に唯一電力を供給している地区になります。
(関連リンク:【福浦地区の合併騒動】)
更に歴史を振りかっていくと、日生自体が元々は兵庫県の移民によって作られた地域とも伝えられています。
実際、方言も岡山弁とは少し違っていて関西訛りが混じったような言葉やイントネーションで、『日生弁』と呼ばれる事もあります。
関連リンク
▶日生駅の駅名の由来
▶備前福河駅の駅名の由来