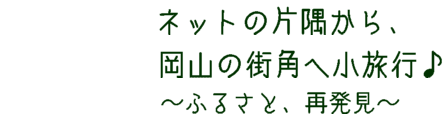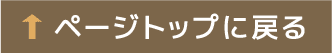TOP>備中県民局エリアの地名の由来>高梁市成羽町吹屋
地名の由来:吹屋(高梁市)
ベンガラの町並み・吹屋
高梁市の山中に、艶やかな赤に染められた町並みがあります。
それが吹屋地区です。
鉱山の捨石から発見された真っ赤な高級塗料にベンガラと いうものがあります。
吹屋はその国内唯一の生産地として知られています。
幕末から明治時代に掛けて賑わったその町並みはベンガラの鮮やかな赤に染められ、今もその面影を残す重要伝統的建造物群保存地区とされています。(岡山県で 初めての指定)
また国の取り組みに先駆けて行われた、地域一帯の景観を保護するための制度である岡山県の『ふるさと村』にも認定されています。
地名の由来
吹屋の地名は、鉱山の町らしいものです。
金属精錬をする事を吹くと呼びます。
『吹く職人』(=鋳物師)が集まっている集落ということから、吹屋となったのです。
鋳物を作る際に、フイゴと呼ばれる空気を送る道具で火力を調整したことから風を送る=吹く=吹く職人となったのだそうです。
いわゆる職人町の地名で、岡山県内では津山市にも吹屋町の地名が残されており、こちらも鋳物師が 住んでいた地域であることに由来しています。
吹屋往来とと道
吹屋の通りを吹屋往来といい、愛称として『とと道』 という名称があります。
これは笠岡港から魚が運ばれて来ていた道である事に由来します。
『とと』は魚の事です。
吹屋は山の奥深い場所にある地域ですが、産出された銅やベンガラを運ぶ人、魚などの食料を運んでくる人などで、非常に賑わっていた そうです。
現在は鉱山町としての賑わいは失われましたが、古い町並みや、立派な木造の小学校校舎などを見に訪れる観光客で賑わう観光地になり ました。
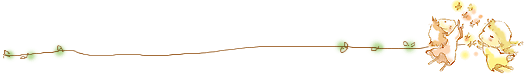
-戻る-
関連リンク
写真:吹屋の風景
写真提供:Googleマップ